作者不明 季:不定 所:肥前国(長崎県)松浦
※始めに、後見が牢屋の作リ物を舞台後方に出す。
九州松浦の某(ワキ)が「私の領内の関の清次という男が、他郷の者と口論して思わず殺してしまった。わざとでないとはいえ、罪人なので牢に入れた」と語る。清次は大変な力持ちなので、某は牢の番人(間狂言)に、用心するよう申し付ける。
牢番が様子を見に行くと、すでに牢破りをして逃げた後だった。某は、清次に妻がいると聞いて、行方を聞き出すため急いで連れてくるよう命じる。
 牢番は、清次の家に行き妻(シテ)を呼び出す。「妻まで罰するとは厳しすぎます」と抗議されるが、なだめて連れて行く。
牢番は、清次の家に行き妻(シテ)を呼び出す。「妻まで罰するとは厳しすぎます」と抗議されるが、なだめて連れて行く。
某は、清次が未明に脱獄したと告げ「夫婦なら知っているだろう」と尋問する。女は「下賎の者ですから、自分が助かることばかり考えたのか、私には何も」と答える。夫を庇っていると見た某は、白状するまで牢に入れることにし、今度はしっかり見張るよう、牢の柱に鼓を掛けて一時ごとに時の数だけ鳴らすよう牢番に命じる。牢番は女を牢に入れ、鼓を掛けると、時を打って去る。
女は牢の中で独り言を言う。「思うことがあるのが外に現れていたのでしょう。包めども袖に溜まらぬ白玉は人を見ぬ目の涙なりけり(包み隠そうとしてもこぼれてしまう真珠は、あなたに会えない私の目の涙だった。古今集)」
牢番が「うるさくて寝られない」と覗くと、女は心労の余り狂気に陥っている。
報告を聞いた某は、女に、なぜ狂気となったのか尋ねる。女は「愚かなことを。一生を約束した人の行方が分からず、自分も肩身が狭い上に牢にまで入れられて、悩みのあまり狂おしくなるのはおかしなことですか」と反発する。某が同情して「夫の居所を言えば牢から出そう」と言うと、「たとえ知っていても、白状して夫を失うものですか。それに、居所は夢にも知りません」ときっぱりと答える。
夫を思う優しさに感動した某は、牢の戸を開け「もうよいから、早く出なさい」と促すが、女は「お志はありがたいですが、夫の身代わりですから。この牢こそ夫の形見」と出ようとしない。会えない夫を偲び、長く添い遂げられない薄い縁を嘆き、取り残されて思い焦がれる我が姿を恥じる。

重ねて促されて牢を出るが「夫はどこなのでしょう」と、髪を乱し涙を流して狂乱の態となる。鼓を見て、何のために鳴らすのか教わって「面白い。古い歌に 時守の打ちます鼓声聞けば時こそ移れ君は遅くて(時守が打つ鼓を聞けば、ずいぶん時間が経ったようだ、あなたはまだ来ないのに。原歌:万葉集)」と詠じ、再び狂乱して打ち鳴らす。その有様は、中国の娥皇・女英の故事(皇帝舜の妃。夫の死を悼んで流した涙が青竹の葉をまだらに染めたという)を思わせるほどである。
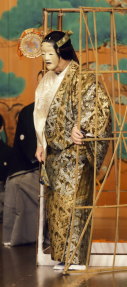 女は鼓を打ちながら狂い舞い、時刻が移っていく。日暮れ時には六つ鼓を打ち、宵には五つの鼓を、偽りの誓いを嘆き「夫も私の様に密かに泣いているだろうか」と、柔らかく打つ。深夜の四つの鼓では「世の中に恋や恨みというものさえなければ」と嘆き、真夜中の九つになると、ついに恋しい夫の面影の幻が見える。
女は鼓を打ちながら狂い舞い、時刻が移っていく。日暮れ時には六つ鼓を打ち、宵には五つの鼓を、偽りの誓いを嘆き「夫も私の様に密かに泣いているだろうか」と、柔らかく打つ。深夜の四つの鼓では「世の中に恋や恨みというものさえなければ」と嘆き、真夜中の九つになると、ついに恋しい夫の面影の幻が見える。
女は「ああ嬉しい、せめて身代わりに立ってこそ、夫婦になった甲斐もある。愛おしいこの牢よ」と、自分で牢屋に戻って、戸を閉めて座り込んでしまう。
あまりの様子に、某は夫婦共に命を助けることを、八幡神に誓って請け合う。それを聞いて、女は落ち着いて「本当は、夫は筑前(福岡県)の大宰府の知人の所に行ったのでしょう」と告白し、牢から出る。某が「我が親の十三回忌の供養のために、恩赦を与える」と告げると、女は慈悲に感謝して手を合わせる。
その後、女はすぐに夫を探し出し、もとの所に帰って末永く暮らしたのだった。